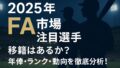阪神タイガースの本拠地として知られる「甲子園球場」。日本で最も歴史のある球場として、プロ野球だけでなく高校野球でも数々の名場面を生み出してきました。この記事では、阪神ファンなら知っておきたい甲子園球場の特徴や歴史、アクセス方法、そして観戦前後に楽しめる周辺スポットまで、まるごとご紹介します。
「甲子園ってどんなところ?」「一度行ってみたいけど不安…」そんな方にもわかりやすく解説していますので、観戦初心者の方にもおすすめです!
\人気商品はコレ!/ 楽天ランキングページはこちら<PR>
\人気アイテムをチェックしよう!/ Amazon売れ筋ランキングはこちら<PR>
阪神タイガースと甲子園球場の深いつながり
阪神タイガースの本拠地としての甲子園
甲子園球場は、1936年から阪神タイガースの本拠地として使用されています。もともとこの球場は高校野球のために作られたものでしたが、プロ野球がスタートしてすぐに、阪神(当時の大阪タイガース)はこの球場を本拠地に選びました。以来、80年以上にわたってタイガースのホームとして愛され続けています。
甲子園球場が他の球場と大きく違うのは、その歴史と伝統です。コンクリートのスタンド、黒土のグラウンド、アルプス席の応援など、どれをとっても独特で、野球ファンなら一度は訪れたい「聖地」として知られています。
また、ファンの熱気も特別です。シーズン中、平日でもスタンドは黄色と黒に染まり、大声援が響き渡ります。甲子園での阪神戦は、選手たちにとっても特別な思いがあるとよく語られます。それだけファンと球団の絆が深い証拠です。
甲子園は単なるスタジアムではなく、阪神ファンの「心のよりどころ」となっているのです。
タイガースと甲子園の伝説的名場面
甲子園で繰り広げられた阪神の名勝負は数え切れません。特に1985年、阪神が日本一に輝いた年は、甲子園にとってもタイガースにとっても歴史的瞬間でした。バース、掛布、岡田のクリーンナップが繰り出す猛打に、ファンは歓喜の渦に包まれました。
また、2003年や2005年のセ・リーグ優勝も記憶に新しいでしょう。特に2003年の星野仙一監督によるチーム再建は、感動を呼びました。その年の甲子園は、連日超満員で、ファンの熱狂が空気を揺らしていました。
さらに、阪神ファンの間で語り草となっているのが「伝説のバックスクリーン3連発」。1985年、巨人戦でバース・掛布・岡田が3連続ホームランを放った試合は、まさに甲子園史上に残る名シーンです。
こうした場面は、甲子園のスタンドにいたファンの記憶に深く刻まれ、語り継がれていくのです。
球団とファンをつなぐ聖地
甲子園はただの野球場ではありません。阪神タイガースとファンをつなぐ「聖地」です。毎年、開幕戦や重要な試合には、遠方からも多くのファンが甲子園を訪れます。それは、ここが阪神ファンにとって“帰ってくる場所”だからです。
試合がない日でも、甲子園球場の周辺を歩いてみると、ファンが記念撮影をしていたり、スタジアムショップでグッズを選んだりしています。応援グッズを持ったファン同士が自然と会話を交わす光景も見られます。
また、甲子園にはファンのための「甲子園歴史館」もあり、ここでは阪神タイガースの歩みをじっくりと学ぶことができます。過去の名選手のユニフォームや、貴重な映像資料も展示されています。
こうした環境が、甲子園を単なる観戦場所ではなく、ファンと球団の「心の交流の場」として特別な存在にしているのです。
高校野球との共存と影響
甲子園球場は、阪神タイガースの本拠地であると同時に、春と夏の高校野球全国大会の開催地としても知られています。高校球児たちにとって、甲子園は「夢の舞台」。そしてその熱戦の合間をぬって、阪神の試合が行われるという共存体制が取られています。
この特別な運用は、他のプロ野球球場には見られない特徴です。高校野球の開催期間中、グラウンドの整備や芝生の手入れなどは一層丁寧に行われ、甲子園の職人たちの技が光ります。
また、高校野球で活躍した選手が数年後に阪神のユニフォームを着て、同じ甲子園でプレーするというドラマもよく見られます。ファンにとってもその成長を見守るのは大きな楽しみです。
このように、甲子園はプロとアマチュアが共に使う“特別な球場”として、多くの人に愛されています。
阪神ファンにとっての“甲子園愛”とは
阪神ファンにとって、甲子園球場は単なる観戦場所ではありません。「人生の一部」と言っても過言ではないでしょう。応援歌を歌い、六甲おろしを叫び、勝利の瞬間にハイタッチを交わす——。そのすべてがファンの人生の記憶になります。
特に印象的なのが、雨の日でもレインコートを着て球場に駆けつけるファンの姿。どれだけチームが不調でも、甲子園に足を運ぶファンの情熱は変わりません。この「どんな時でも応援する姿勢」が、阪神ファンの特徴であり、甲子園の雰囲気を作り上げています。
また、親子三世代での観戦、学生時代から通い続ける人など、それぞれの“甲子園ストーリー”が存在します。それだけ、甲子園には人の心を動かす何かがあるのです。
甲子園球場の歴史と進化の軌跡
甲子園球場が誕生した背景
甲子園球場が誕生したのは1924年(大正13年)。当時はまだプロ野球が存在しておらず、全国中等学校優勝野球大会(現在の夏の高校野球)のために作られたスタジアムでした。当初の名称は「阪神甲子園球場」で、甲子園という地名が名前の由来です。
建設のきっかけは、大会の人気が急上昇し、観客が増え続けていたこと。これまで使用していた豊中球場では対応できなくなったため、より大きく、観戦しやすい施設が必要となりました。そこで、阪神電気鉄道(現・阪神電鉄)が私財を投じて球場を建設し、沿線の集客アップにもつなげようと考えたのです。
完成当時の収容人数は約5万人で、当時としては日本最大級のスタジアムでした。広いスタンドと、天然芝、黒土のグラウンドが話題となり、「野球の殿堂」として注目を集めました。現在でも、約100年前に作られた球場とは思えないほどの魅力を保っています。
このように、甲子園球場は最初から「特別な目的のために生まれた球場」だったのです。
昭和・平成を彩ったリニューアルの歩み
甲子園球場は、その長い歴史の中で何度もリニューアルを重ねてきました。特に大きな変化があったのは、2007年から2010年にかけて行われた「大改修」です。この改修によって、老朽化していたスタンドが全面的にリニューアルされ、トイレや売店などの施設も現代的なものへと生まれ変わりました。
外観に使われていたツタの一部を保存しつつ、新しい外壁にはレンガ風のデザインが採用され、歴史とモダンの調和が取られています。さらに、バックネット裏の座席を広くし、ゆったりと観戦できるようになったことで、家族連れや年配のファンにも優しい球場となりました。
また、バリアフリー対応も進み、エレベーターや車椅子用観戦スペースなどが整備されています。ナイター照明のLED化やスコアボードの高解像度化など、時代のニーズに合わせた進化を続けています。
このような改修によって、甲子園球場は「古くて新しい」スタジアムとして、今なお多くの人に愛されているのです。
高校野球とプロ野球の共存の歴史
甲子園球場の最大の特徴は、高校野球とプロ野球が共に使用していることです。春の選抜大会(センバツ)と夏の全国選手権大会の期間中は、阪神タイガースはビジター試合や京セラドームなどでの代替試合を行い、球場を高校球児に譲ります。
この特別な共存関係は、日本の野球文化において非常に重要なものです。高校野球が終わった後、プロの選手たちが同じグラウンドに立つ——それはまさに夢のリレーと言えるでしょう。
また、阪神の選手にも甲子園での高校野球経験者が多く、「甲子園でプレーする特別な気持ち」を理解しています。こうした背景があるからこそ、甲子園の試合には独特の緊張感と感動が生まれるのです。
そして、グラウンド整備のプロたちも高校野球終了後すぐに土や芝を整え、プロの試合に間に合わせる技術と努力は見事の一言。まさに「プロとアマが本気で向き合う球場」として、甲子園は日本の野球文化の象徴と言えるでしょう。
「聖地」の名にふさわしい数々の伝説
甲子園球場は、多くの伝説を生んできました。それは阪神タイガースだけでなく、高校野球でも数えきれない名場面がこの場所で生まれています。延長戦の末に劇的なサヨナラ打、高校生のノーヒットノーラン、スタンドを埋め尽くす応援団の涙と歓喜——その一つ一つが甲子園の伝説です。
プロ野球では、巨人との伝統の一戦や、優勝を決めた試合、引退する選手が最後の打席に立つシーンなど、どれも心に残る瞬間ばかり。これらの出来事が重なることで、甲子園は単なる球場を超えて「野球の神が宿る場所」として語られるようになったのです。
また、テレビ中継やニュースで見るあの「甲子園の風景」は、多くの人にとって懐かしさや感動を呼び起こします。それは一度訪れただけでも心に残る、特別な空間だからです。
こうした数々の伝説が、甲子園を「聖地」と呼ばせるにふさわしい存在にしているのです。
近代化と伝統のバランス
甲子園球場は、現代化を進めながらも「古き良き伝統」を大切にしている球場です。先ほど触れたように、大規模リニューアルによって座席や設備は現代的に改装されましたが、球場独自の雰囲気はしっかりと守られています。
たとえば、外野の応援席では今も太鼓とトランペットの鳴り物応援が続けられており、球場全体が一体感に包まれます。これは他の球場にはない「甲子園ならではの文化」です。
また、黒土のグラウンドや外野フェンスの低さ、手動式の得点板など、懐かしい要素も一部に残されています。最新技術を導入しつつ、あえてアナログな部分を残すことで、ファンが「変わらない甲子園の良さ」を感じられるのです。
このように、甲子園球場は「進化」と「伝統」を絶妙なバランスで両立させている、世界でも珍しい球場のひとつなのです。
甲子園球場の特徴を徹底解剖
全国的にも珍しい球場構造
甲子園球場の構造には、他の球場にはない独自の魅力があります。まず最大の特徴は、左右非対称な形状。通常の球場では、左右のフェンスまでの距離がほぼ同じで設計されることが多いですが、甲子園はライト側が狭く、レフト側が広いという非対称構造になっています。
この構造のため、右打者と左打者でホームランの出やすさが異なり、選手たちの戦術や打撃スタイルにも影響を与えています。阪神タイガースでは、ライトスタンドにホームランを放てる左打者が活躍しやすいとも言われています。
また、外野フェンスの低さも特徴です。フェンスが低いため、ファンとの距離が近く、打球の行方がはっきり見えるという魅力があります。ファウルグラウンドも広めで、守備にとっては少し有利な設計です。
さらに、内野スタンドからの角度が急で、グラウンド全体がよく見渡せる構造になっているため、どの席からでも試合を楽しめるのが魅力です。これらの構造は、観戦するファンにも、プレーする選手にも、それぞれ独特の体験を提供してくれます。
グラウンドの土と芝のこだわり
甲子園球場といえば「黒土のグラウンド」。この黒土は、他のプロ野球球場ではほとんど見られない特別な素材です。雨に強く、柔らかすぎず硬すぎない性質があり、ボールのバウンドが安定しているのが特徴です。
黒土には、岡山県産や広島県産など数種類の土が混合されており、毎年の使用状況に合わせて微調整が行われています。この土は、高校野球終了後に選手が「記念に持ち帰る」ことで有名になり、甲子園の象徴のひとつにもなっています。
また、芝についても徹底した管理がされています。現在の甲子園球場では「ティフトン芝」という強い芝が使用されており、選手が激しく走っても剥がれにくく、夏の高温にも耐える設計になっています。毎日グラウンドキーパーたちが丹精込めて水やり・刈り込み・目土入れを行っており、そのこだわりはプロの技そのもの。
この土と芝の管理は、甲子園のプレーの質を高め、選手の安全性にも寄与しています。まさに「一流の舞台」としての品質が保たれているのです。
鳴り物応援とファン文化
甲子園球場を語るうえで欠かせないのが、応援スタイルの特徴です。特に阪神ファンによる「鳴り物応援」は全国でも有名で、太鼓やトランペットが鳴り響くスタンドはまさに圧巻。攻撃のときは選手ごとの応援歌が歌われ、スタンドが一体となってチームを後押しします。
この応援は、観戦初心者でもすぐに馴染めるよう、メガホンやチラシで歌詞や振り付けが紹介されていることもあります。また、試合中に流れる「六甲おろし」は、阪神ファンの魂とも言える存在で、勝利時にはスタンド全体で大合唱が巻き起こります。
さらに、ファン同士の連帯感も特徴的です。初めて観戦に来た人でも、隣の席のファンが親切に応援のタイミングを教えてくれるなど、温かい雰囲気が広がっています。
このような「ファンの一体感」があるからこそ、甲子園は特別な場所として、多くのファンに支持され続けているのです。
球場グルメの人気メニュー
甲子園球場は、グルメの充実度も魅力のひとつです。スタンド内の売店やフードブースでは、さまざまなグルメが楽しめ、野球観戦に欠かせない「もうひとつの楽しみ」として親しまれています。
中でも人気なのが「甲子園カレー」。濃厚なルーに大きめの具がゴロゴロ入っていて、ボリューム満点。スタンド席で食べると、なぜか一段と美味しく感じられると評判です。
また、焼き鳥や唐揚げ、たこ焼きといった定番メニューもあり、香ばしい匂いが漂うスタンドはまさに屋台村のよう。ビールとの相性も抜群で、観戦中のリフレッシュにもぴったりです。
さらに、最近では女性向けにスイーツやヘルシーメニューも増えており、アイスクリームやフルーツボウルも販売されています。子ども向けのお弁当もあり、家族連れでも楽しめるよう工夫されています。
このように、甲子園のグルメは「味」だけでなく「観戦体験の一部」として進化し続けているのです。
外野席からの風景と観戦ポイント
甲子園球場の外野席は、阪神ファンの応援の中心地。特にライトスタンドは「応援の聖地」として知られ、熱狂的なファンが集まる場所です。応援団の中心となって太鼓や旗を振り、選手を鼓舞する様子は、まるでライブコンサートのような熱気です。
一方で、初めて観戦する方には「アルプス席」や「内野席」もおすすめ。全体を見渡せるバランスの良い視界が特徴で、プレーの流れをじっくり楽しみたい方にぴったりです。
外野席から見る打球の軌道やスタンドインの瞬間は、まさに甲子園ならではの醍醐味。夕暮れ時にライトアップされた球場の美しさも格別で、写真映えも抜群です。
【観戦ポイント早見表】
| 座席種別 | 特徴 | おすすめタイプ |
|---|---|---|
| ライト外野席 | 応援が最も熱い | 熱狂的ファン向け |
| レフト外野席 | ビジターファンが多い | 他球団のファン向け |
| アルプス席 | 応援と観戦のバランス◎ | 初心者・家族向け |
| 内野席 | プレイが近く見える | ゲーム展開重視派向け |
このように、座席によって楽しみ方がまったく違うのも、甲子園ならではの魅力です。
甲子園球場までのアクセス完全ガイド
電車での行き方(梅田・なんば・三宮から)
甲子園球場へ行くなら、もっとも便利なのは電車です。特に阪神電鉄本線の「甲子園駅」が最寄駅で、駅を降りて徒歩5分以内というアクセスの良さが魅力です。主要な都市からのアクセス方法は以下の通りです。
-
梅田駅(大阪)から:阪神本線「梅田駅」から直通特急で約15分。乗り換え不要で非常にスムーズです。
-
なんば駅から:阪神なんば線を利用して、尼崎駅で阪神本線に乗り換え、合計で約25~30分ほど。
-
三宮駅(神戸)から:阪神本線の直通特急で約20分。乗り換えなしで快適です。
特に阪神電車は「タイガースラッピング電車」も運行されており、乗車中から気分が盛り上がること間違いなし。試合前後には臨時列車が運行されることもあり、大規模イベント時にも対応しています。
また、電車は試合終了後も本数が多く、帰宅の際にも安心です。駅の改札を出れば、球場へ向かう人の流れがすぐにわかるため、初めての人でも迷う心配はありません。
バス・タクシー利用のコツ
電車以外にも、バスやタクシーを使って甲子園球場にアクセスする方法があります。特に周辺地域からアクセスする場合や、雨天時・荷物が多い場合に便利です。
【バス利用のポイント】
阪神バスや阪急バスが甲子園駅や球場前まで運行しています。特に西宮や尼崎方面からは、バス1本でアクセスできるルートも多く、地元の方に利用されています。ただし、試合開始直前や終了直後は道路が混雑するため、所要時間には余裕を持って行動しましょう。
【タクシー利用の注意点】
甲子園駅周辺にはタクシー乗り場がいくつかありますが、試合終了後はかなりの混雑が予想されます。アプリを使ってタクシーを呼ぶ場合は、周辺の混雑を避けて、少し離れた場所で乗るのがおすすめです。
また、球場周辺は試合開催日に交通規制がかかることがあるので、ドライバーと事前にルートを相談しておくと安心です。
車で行く場合の駐車場情報
甲子園球場には専用の駐車場がありません。そのため、車でのアクセスを考えている方は、周辺のコインパーキングや事前予約型の駐車場を利用する必要があります。
【代表的な駐車場】
-
タイムズ甲子園プラス(徒歩約3分)
-
NPC西宮甲子園第2駐車場(徒歩約5分)
-
三井のリパーク 甲子園七番町駐車場(徒歩約8分)
これらの駐車場は、試合開催日には非常に混雑するため、akippa(アキッパ)や特Pといった駐車場予約サービスの利用がおすすめです。事前に予約しておけば、当日のトラブルを避けられます。
また、甲子園球場周辺は一方通行が多く、道が狭い場所もあるので、運転には十分注意してください。帰りの渋滞も考慮し、早めの出発・早めの到着を意識すると安心です。
混雑を避けるおすすめの時間帯
甲子園球場は全国からファンが集まる人気スポット。そのため、試合当日はかなりの混雑が予想されます。できるだけ快適に観戦したいなら、混雑時間を避けて行動するのがポイントです。
【行き(試合前)】
-
一般的に、試合開始の1時間半前までに到着するのがベスト。
-
混雑ピークは開始30分前~直前なので、この時間帯は避けましょう。
-
グッズショップやグルメもゆっくり楽しみたいなら、2時間前到着がおすすめ。
【帰り(試合後)】
-
試合終了直後は駅が非常に混雑します。
-
駅周辺で少し時間を潰して、30分ほど待ってから移動するとスムーズです。
-
周辺のカフェやグッズショップ、甲子園歴史館などで時間を過ごすのも◎。
また、平日ナイターでは、仕事帰りのサラリーマン層が多く、開始直前は特に混雑します。早めに会場入りしておくと、落ち着いて観戦準備ができます。
試合後のスムーズな帰宅方法
試合後は、多くのファンが一斉に駅へ向かうため、非常に混雑します。特に土日祝やナイターの終了後は、甲子園駅の改札で長蛇の列ができることも珍しくありません。
【おすすめの帰宅テクニック】
-
駅直行を避ける:少し球場の外で時間を調整し、ピークをずらす。
-
周辺スポットで時間を潰す:甲子園歴史館や飲食店で1時間ほど待機。
-
1駅歩いてから乗車:例えば「久寿川駅」や「鳴尾・武庫川女子大前駅」まで歩けば、混雑を避けやすいです。
【裏技】として、JR甲子園口駅まで歩くというルートもあります(徒歩30分ほど)。電車の本数は少ないですが、阪急・JR線への乗り換えには便利な場合も。
以上のように、試合終了後の時間の使い方次第で、帰宅のストレスを大幅に減らすことができます。
甲子園をもっと楽しむ周辺スポット
甲子園歴史館の見どころ
甲子園球場に来たら、ぜひ立ち寄ってほしいのが「甲子園歴史館」です。球場の3塁側スタンド内にあり、阪神タイガースの歴史や高校野球の名場面、甲子園球場の歩みなどが展示されています。
館内には、昭和初期の写真から現代までのユニフォームやグローブ、バットなどの貴重な実物展示が並びます。阪神タイガースファンにはたまらない、過去の名選手の紹介コーナーや、優勝時の記念映像も観られ、まさに“聖地”の裏側を知ることができます。
特に人気なのが、バーチャルバッティング体験や、選手のロッカーを再現したコーナー。子どもから大人まで楽しめる工夫が満載です。高校野球コーナーでは、感動の名勝負が映像で紹介され、まるでその場にいるかのような臨場感があります。
入場料は大人900円、高校生以下500円(2025年時点)とリーズナブル。試合の前後に1時間ほどで見学できるので、スケジュールにも組み込みやすい施設です。
ファンに人気のグッズショップ
甲子園周辺には、阪神タイガースの公式グッズを取り扱うショップが多数あります。なかでも有名なのが、球場敷地内にある「阪神タイガースショップ」や「T-SHOP(ティーショップ)」。試合日には長蛇の列ができることも珍しくありません。
販売されているアイテムは、定番のユニフォームやキャップ、タオルから、日替わりで登場する限定アイテムまでさまざま。特に人気選手の応援グッズは早めに売り切れてしまうので、早めにチェックするのがコツです。
最近では、女性ファン向けのファッショナブルな応援グッズや、おしゃれな雑貨も豊富に取り揃えられており、観戦だけでなくショッピング目的で訪れる人も増えています。
また、子ども向けのキッズコーナーや、赤ちゃん連れでも楽しめるベビーグッズなど、家族みんなで楽しめるラインナップも充実しています。観戦の思い出として、グッズショップでの買い物は外せないポイントです。
球場周辺のおすすめ飲食店
甲子園球場の外にも、魅力的な飲食店がたくさんあります。観戦前後に腹ごしらえしたい人には、ローカルの味を楽しめるお店がおすすめです。
【地元で人気のお店例】
-
ピザウルス甲子園:子連れ歓迎のアットホームなピザ専門店。持ち帰りもOK。
-
元祖たこ八:関西風のふわとろたこ焼きが名物。試合帰りにぴったり。
-
甲子園一番街のうどん店「大和」:出汁がきいたうどんが評判。並んでも食べたい一品。
さらに、球場のすぐ近くには「ららぽーと甲子園」もあり、ファストフードからスイーツまで幅広いジャンルの食事が楽しめます。イートインスペースもあるので、家族連れでも安心です。
ナイター観戦の前には、少し早めに来て近くのお店でディナーを楽しむのも良いでしょう。地元の味とともに、甲子園観戦をより特別な思い出にできます。
観戦前後に立ち寄れる観光スポット
甲子園球場を訪れる際には、近隣の観光スポットにも足を延ばしてみましょう。野球以外にも楽しめる場所がたくさんあります。
【おすすめスポット】
-
西宮神社(えべっさん):商売繁盛の神様として有名で、開運祈願にも◎。
-
夙川(しゅくがわ)公園:桜の名所で、季節ごとの自然散策が楽しめます。
-
キッザニア甲子園:子ども向けの職業体験テーマパーク。家族での甲子園観戦とセットで大人気。
また、阪神電車で数駅の距離にある「尼崎城」や「神戸・三宮」へのアクセスも良好。観戦と観光をセットにすれば、一日中充実した時間を過ごすことができます。
試合までの時間に余裕があれば、こうしたスポットを巡ってから球場入りするのもおすすめです。
地元住民おすすめの裏ルート情報
甲子園周辺は、観戦日にはとにかく混雑します。そんなときに役立つのが、地元の人たちがよく使っている“裏ルート”です。
【アクセス裏技】
-
甲子園駅の混雑回避ルート:試合後は「久寿川駅」や「鳴尾・武庫川女子大前駅」まで歩くことで、比較的スムーズに帰れます。
-
グッズ購入の裏タイミング:試合開始直後はショップが空いていることが多く、ゆっくり選べる穴場時間です。
-
トイレ混雑回避法:スタジアム外の公園やららぽーとのトイレを活用するのが◎。
また、周辺のコンビニも試合前後は混みがちなので、飲み物や軽食は事前に購入しておくのが賢明です。
こうした裏ルートを活用すれば、より快適でスマートな甲子園体験ができます。観戦リピーターたちが実践している工夫をぜひ取り入れてみてください。
まとめ:甲子園は阪神ファンの「心のふるさと」
甲子園球場は、単なる野球場ではありません。阪神タイガースの熱狂的ファンにとっては、人生の思い出が詰まった“心のふるさと”であり、毎年新しいドラマが生まれる舞台でもあります。その歴史は1924年の開場から始まり、プロ野球と高校野球の両方で数えきれない名場面を生み出してきました。
球場の構造、グラウンドの土と芝、応援スタイル、スタジアムグルメ、アクセス方法……どれを取っても甲子園は他の球場と一線を画しています。さらに、周辺施設や観光スポットも充実しており、観戦をより楽しい体験へと導いてくれます。
この記事を通して、甲子園球場の奥深い魅力を感じていただけたなら幸いです。まだ行ったことのない方も、何度も足を運んでいるファンの方も、ぜひ改めて甲子園の魅力を体感してみてください。
そして、阪神タイガースとともに、感動の瞬間をその目で見届けましょう。