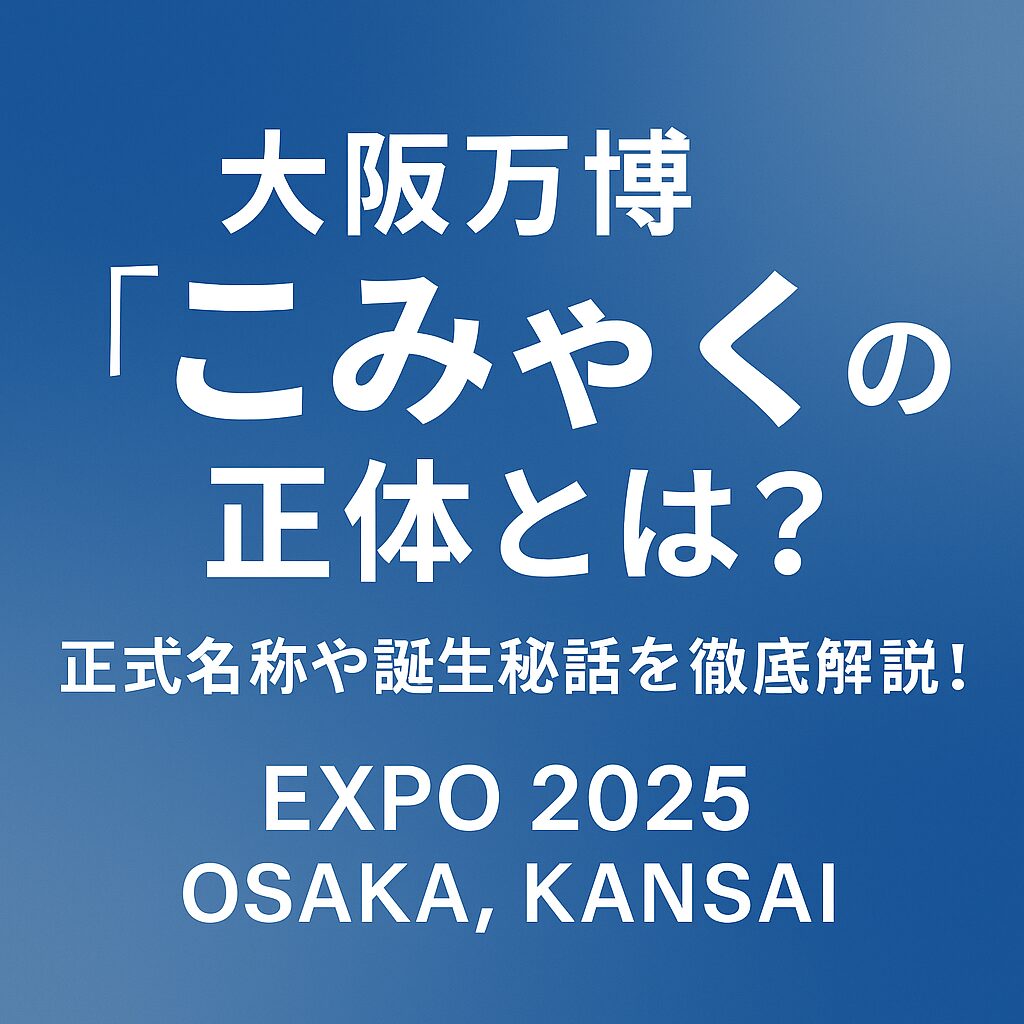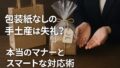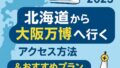2025年大阪・関西万博のキャラクターといえば「ミャクミャク」が有名ですが、実は今、SNSや会場でひそかに人気を集めている存在がいます。その名も「こみゃく」。公式でもない、キャラクターでもないのに、なぜここまで話題になっているのか?今回は、その正体や誕生秘話、ミャクミャクとの違いまで、SNSでも話題沸騰の「こみゃく」のすべてをわかりやすく解説します。万博をもっと楽しくする裏キャラ的存在を、あなたもきっと好きになるはずです。
\人気商品はコレ!/ 楽天ランキングページはこちら<PR>
\人気アイテムをチェックしよう!/ Amazon売れ筋ランキングはこちら<PR>
大阪万博の公式キャラクター「ミャクミャク」とは?
ミャクミャクの正式名称とその意味
2025年大阪・関西万博の公式キャラクターとして誕生した「ミャクミャク」。その正式名称は「ミャクミャク」です。多くの人が「名前が変わってる!」と感じたかもしれませんが、この名前には深い意味が込められています。「ミャクミャク」は、日本語の「脈々(みゃくみゃく)」という言葉から生まれました。この言葉には「途切れることなく受け継がれていく」という意味があり、未来へ続く人類の挑戦やつながりを表現しています。
また、英語での表記も「MYAKU-MYAKU」となっており、世界中の人にも覚えやすく、親しみを持ってもらえることを意識しています。この名前には、生命の流れ、地球の恵み、人類の進化など、様々な「脈」が込められており、万博が掲げる「いのち輝く未来社会のデザイン」を象徴しています。日本独自の感性を世界に発信する意図もあり、名前だけでも話題性を持つことに成功しています。
キャラクターの特徴とデザイン秘話
ミャクミャクのデザインは、一見すると不思議な赤い粒の集合体に見えます。これは実は「細胞」をモチーフにしており、生命の源である水を内包しています。青い部分は水の精霊のような存在で、赤い部分が大阪万博のロゴマークからインスパイアされた形状になっています。生物と科学、自然と未来をつなぐ存在として、あえて不思議でユニークな姿に仕上げたそうです。
デザインを手がけたのは、デザイナーの山下浩平氏。彼は「見た瞬間にインパクトを与えるキャラクター」を目指し、通常のゆるキャラとは異なるアート性の高いデザインに仕上げました。未来の子どもたちが自由に発想できるよう、あえて固定された動物やキャラクターではなく、変幻自在な存在を目指しています。
ミャクミャク誕生の経緯
2022年3月22日、大阪市内でミャクミャクは公式にお披露目されました。公募で集まったデザイン案の中から、厳正なる審査を経て選ばれました。選定理由としては、未来感、親しみやすさ、そして万博のテーマとの親和性が挙げられています。発表当初は「ちょっと怖い」「不思議すぎる」と話題になりましたが、次第にその独特の姿がSNSなどで人気を博し、今では万博の顔として定着しました。
万博のシンボルとしての役割
ミャクミャクは、単なるマスコットキャラクターではなく、大阪・関西万博の象徴的存在です。万博会場内だけでなく、関連イベントやポスター、グッズなどさまざまな場所に登場し、万博の認知拡大に貢献しています。特に、海外からの来場者にも強いインパクトを与えるため、国際的なPR活動にも積極的に活用されています。
ミャクミャクのグッズやイベント登場情報
現在、ミャクミャクをモチーフにしたグッズは多数展開されています。ぬいぐるみ、キーホルダー、Tシャツ、エコバッグなど、様々なアイテムが販売されており、イベント会場やオンラインストアでも購入可能です。また、万博公式イベントや全国のPRイベントにも着ぐるみ姿で登場し、来場者との撮影タイムも人気です。今後はさらにコラボカフェや限定アイテムも登場予定で、ミャクミャクブームはますます加速しそうです。
「こみゃく」とは?SNSで話題の存在
「こみゃく」の見た目と特徴
「こみゃく」は、大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」とよく似た姿をしています。ただし、「ミャクミャク」よりもずっと小さく、かわいらしいサイズ感が特徴です。赤い球体が連なった姿はそのままですが、全体的にコンパクトで、表情もどこかあどけなく見えることから、「ミャクミャクの子ども」として受け止める人が多いです。
会場内では、案内看板や装飾のデザイン要素として登場しており、歩いていると色々な場所で発見できます。公式キャラクターではないものの、その存在感と愛らしさから、SNSでは「こみゃく」と親しまれています。
こみゃくの由来と誕生背景
「こみゃく」は、実は万博会場のデザインの一部として生まれたものです。大阪万博のロゴマークを元にした「デザインエレメント」として、会場内のサインや装飾に使われる目的で制作されました。これは、クリエイティブディレクターの引地耕太氏によるもので、ミャクミャク本体とは別のコンセプトでデザインされています。
ただし、その可愛い見た目から、来場者の間で自然発生的に「ミャクミャクの子ども」=「こみゃく」と呼ばれるようになったのです。特に公式から正式な名称が発表されていなかったこともあり、SNSでこの名前が急速に広まりました。
公式ではない?SNSで生まれた愛称
ポイントは、「こみゃく」は公式のキャラクターでもなければ、公式に認められた名前でもない、ということです。完全にSNS発信の愛称であり、万博の運営側もこの呼び名を黙認している、という立ち位置です。最近では、公式のSNSアカウントでも「こみゃく」と呼ぶようになり、あえてこの親しみやすさを活用しているようです。
このように、市民や来場者が自発的に名付けたキャラクターが話題になることは、近年のイベントやプロモーションでは非常に重要な現象であり、大阪万博でもその例となりました。
会場内での役割と使われ方
会場では、こみゃくは案内板や誘導サイン、装飾の一部としてあちこちに登場しています。例えば、トイレの場所を案内したり、写真スポットの目印になっていたり、来場者の動線を楽しくナビゲートする役割を担っています。まさに「探して楽しい」存在として、こみゃくを見つけることが来場者の新たな楽しみ方にもなっています。
SNSでの人気とファンの反応
SNS上では、「#こみゃく」のハッシュタグで、多くの投稿が見られます。ファンアートやぬいぐるみ制作、コスプレなど、ファンによる独自の盛り上がりが起きており、公式以上に熱量を持ったコンテンツが生まれています。このように、こみゃくは市民や来場者から愛される「非公式マスコット」として、万博の新しい楽しみ方を提供しています。
「こみゃく」の正式名称はあるのか?
公式サイトや資料から調べた結果
「こみゃく」という呼び名が広まったものの、実際に公式サイトや関連資料を調べてみると、この名前は正式には存在していないことが分かります。大阪・関西万博の公式キャラクターとして登録されているのは「ミャクミャク」のみであり、「こみゃく」に関する記載は一切ありません。
公式のプレスリリースやパンフレットにも「こみゃく」という名前は使われておらず、完全に来場者やSNSユーザーが勝手に呼び始めた名称ということになります。
ただし、会場内で見かける「こみゃく」の姿は、公式の会場デザインの一部であり、一定の意図を持って設置されています。つまり、名前は非公式ながら、その存在は公式が認める会場デザインの一要素なのです。
デザインエレメントIDとは何か?
「こみゃく」の正体は、正式には「デザインエレメントID」と呼ばれる、会場内で使用されるデザインのパーツです。これは、ロゴマークをモチーフにして作られており、案内板やサイン、装飾などに統一されたデザインとして組み込まれています。
「デザインエレメントID」は、あくまで会場を訪れる人が迷わず、楽しく歩けるように工夫されたグラフィックパーツの集合体であり、キャラクターではありません。しかし、その見た目があまりにも「ミャクミャク」に似ているため、自然と「こみゃく」と呼ばれるようになったのです。
引地耕太氏によるデザインの意図
このデザインを手掛けたのは、クリエイティブディレクターの引地耕太氏です。引地氏は、会場内の体験がよりワクワクするものになるように、キャラクターのような存在感を意識しつつも、あくまで案内機能を果たす存在としてデザインしたと語っています。
本来は「キャラクター」ではないのですが、来場者が勝手に親しみを持って名前を付け、SNSで盛り上がることで、結果的にキャラクターのような役割を果たすことになったのは、嬉しい誤算だとも言われています。
万博ロゴとの関係
「こみゃく」のデザインの元になっているのは、大阪万博の公式ロゴマークです。このロゴは赤い球体が連なった独特な形状をしており、ミャクミャクのデザインもこれを踏襲しています。そのため、「こみゃく」も必然的にこのデザインを引き継ぐ形となり、より一層「ミャクミャクの子ども」として認識されることになったのです。
このロゴマークは「細胞」や「いのちの輝き」を象徴するもので、こみゃくのデザインもその延長線上に位置しています。
なぜ「こみゃく」と呼ばれるようになったか
では、なぜ「こみゃく」という名前が生まれたのでしょうか。その理由はシンプルです。「ミャクミャク」の小型版だから「子ミャク」→「こみゃく」と呼ぶようになったのです。SNSでは、初めて見た人たちが「これってミャクミャクの子ども?」と投稿したことがきっかけで、その呼び名が爆発的に広まりました。
この流れは、現代のSNS文化においてよく見られる現象で、公式よりもファンやユーザーの間で自然に名前が付くことで、より愛着を持たれる存在になるケースが増えています。こみゃくもその代表例と言えるでしょう。
こみゃくとミャクミャクの違いを徹底比較
サイズ・役割の違い
まず、こみゃくとミャクミャクの最大の違いは「サイズ」と「役割」です。ミャクミャクは万博の公式キャラクターとして、メインステージやイベント、ポスター、グッズなどで主役級の扱いを受けています。一方で、こみゃくは会場内のデザイン要素で、案内板や標識などにさりげなく登場します。存在感も控えめで、会場を訪れた人が「どこかで見たことがある?」と気づく程度のさりげなさが特徴です。
サイズも違い、ミャクミャクは大きな着ぐるみとして登場しますが、こみゃくは看板や壁面装飾、デジタル表示などに描かれるのみ。こみゃく単体で歩いたり、動いたりすることはありません。そのため、役割的には「主役」と「サポート役」という関係性に位置付けられるでしょう。
デザインの違いと共通点
デザイン面では、どちらも大阪万博のロゴマークを元にしているため、赤い球体が連なる形状は共通しています。しかし、ミャクミャクはその球体の集合体が独特の表情を持ち、青い水の姿も融合させたデザインとなっています。つまり、「いのち」や「水」を象徴する存在であり、生命体のようなキャラクター性を持っています。
こみゃくはそれに比べ、よりシンプル。青い水の要素はなく、赤い球体だけで構成されています。表情や動きも想定されておらず、静的な存在です。この違いが、ミャクミャクはキャラクター、こみゃくはデザインエレメント、という位置づけの違いに直結しています。
こみゃくはどこで見られる?
こみゃくは、万博会場のいたるところで見ることができます。案内標識、エリアマップ、施設の入り口、トイレの案内など、実用的な表示物の中に組み込まれています。また、写真スポットの装飾や、ARコンテンツの中にも登場するなど、来場者が「探して楽しむ」存在になっています。
ミャクミャクのように「ここで必ず会える」という場所は設定されていませんが、こみゃくはむしろ、会場内を歩き回ることで偶然出会える楽しさがあります。この発見型の存在が、こみゃくならではの魅力とも言えるでしょう。
ファンから見た2つのキャラクター
ファン目線で見ると、ミャクミャクは公式キャラクターとして「主役」であり、グッズも豊富。こみゃくは「裏キャラ」的な位置づけで、非公式グッズやファンアートで愛されています。この違いは、ファン文化において非常に重要です。
「公式ではないけど、みんなが好き」という存在は、逆に強いコミュニティを生むことがあります。SNSでは、こみゃくをテーマにした4コマ漫画や、ファンが勝手に作ったぬいぐるみなども登場し、ミャクミャクとは違った角度で愛されているのです。
万博体験をもっと楽しくする存在
こみゃくの存在は、万博体験をより楽しいものにしています。会場を歩いていると、ふとこみゃくに出会い、思わず写真を撮りたくなる。その瞬間、ただ歩くだけだった体験が、ちょっとした宝探しのようなワクワクに変わります。
ミャクミャクだけではなく、こみゃくの存在があることで、万博会場全体が「遊び心にあふれた空間」として演出されているのです。この隠れキャラ的な役割は、近年の大型イベントでも人気の手法で、来場者の満足度向上に一役買っていることは間違いありません。
まとめ:「こみゃく」は親しみを生む存在だった
万博での楽しみ方が増える理由
大阪・関西万博には、公式キャラクターの「ミャクミャク」だけでなく、隠れた存在「こみゃく」がいることで、来場者の楽しみ方が一層広がります。公式サイトやガイドブックには載っていない、現地でしか発見できない存在として、こみゃくは会場内での冒険心を刺激してくれるのです。こみゃくを探しながら歩くだけでも、思わぬ発見があったり、写真を撮ったりと、よりアクティブに会場を巡るきっかけになります。
これは、単に展示を見るだけではなく、「探して楽しむ」という新しい参加型の体験を生み出すことで、万博そのものをもっと親しみやすいイベントにしてくれる要素でもあります。
こみゃく探しの楽しみ方
こみゃくを探す楽しみ方はとても簡単です。会場内の案内板、トイレや飲食ブースのサイン、フォトスポットなどを注意深く見てみましょう。赤い球体が連なった可愛いデザインのこみゃくが、あちこちに隠れています。また、イベントによっては、こみゃくをテーマにしたスタンプラリーやARアプリなども展開される予定です。
SNSでも「#こみゃく」で情報収集すれば、他の来場者が見つけたこみゃくスポットが紹介されています。友達同士で「どれだけこみゃくを見つけられるか」を競ったり、写真を撮って投稿するなど、来場の思い出作りにもぴったりです。
グッズやフォトスポット情報
現時点では、こみゃくの公式グッズは存在しません。しかし、ミャクミャク関連のグッズ売り場には、こみゃく風のデザインが使われているアイテムもあり、ファンの間ではこみゃくをイメージした手作りグッズや雑貨が話題になっています。
また、会場内にはこみゃくと一緒に撮影できるフォトスポットも登場する予定で、今後さらに注目度が高まりそうです。非公式ながら、ファンアート展などの企画も進んでいるとの噂もあり、ますます存在感を強めています。
万博運営側の反応と狙い
運営側も、こみゃくに関しては公式なコメントを避けつつも、SNSなどで話題になっていることを歓迎しているようです。意図的に「公式ではない隠れキャラ」を作ることで、来場者が自由に楽しめる余白を生み出しており、これは近年のイベント運営でよく用いられる手法です。
公式がすべてを用意するのではなく、来場者自身が発見し、広げていく文化を促進することで、イベントへの愛着が生まれ、SNSでの話題も自然に拡散されます。こみゃくは、まさにその成功例といえるでしょう。
万博がもっと身近になる存在として
「こみゃく」は、大阪・関西万博をもっと身近に感じさせてくれる存在です。公式のミャクミャクが未来社会や命のつながりという壮大なテーマを背負っているのに対し、こみゃくはそれをちょっと砕けた形で表現し、来場者の日常感覚に寄り添ってくれます。
こみゃくを通じて、会場の隅々まで楽しく探検し、SNSで思い出を共有し、友達と盛り上がる。そんな体験が、大阪・関西万博を「ただの展示イベント」ではなく、「自分ごと」として楽しめる理由になっているのです。
まとめ
2025年大阪・関西万博では、公式キャラクター「ミャクミャク」が注目を集める中、もうひとつ話題になっている存在が「こみゃく」です。この「こみゃく」は、実は公式に認められたキャラクターではなく、会場内のデザイン要素の一つ。しかし、その愛らしい姿と、ミャクミャクの子どものような見た目から、来場者やSNSユーザーの間で自然と「こみゃく」という名前で親しまれるようになりました。
正式名称は「デザインエレメントID」というもので、万博ロゴマークをモチーフに、会場内で案内や誘導の役割を担っています。ミャクミャクのようにイベントで歩いたり、グッズが販売されたりすることはありませんが、こみゃくはその存在感で多くの来場者の心をつかんでいます。
また、SNSでは「#こみゃく」を使った投稿が多数見られ、ファンによるグッズ制作やアート作品も増えており、こみゃくは非公式ながらも万博体験をより楽しく、親しみやすいものにしています。
このように、こみゃくは公式・非公式の枠を超えて、人々が自分たちの手で楽しみ方を作り出している、まさに現代のイベント文化を象徴する存在になっているのです。万博に行くなら、ぜひこみゃく探しも楽しんでみてください。