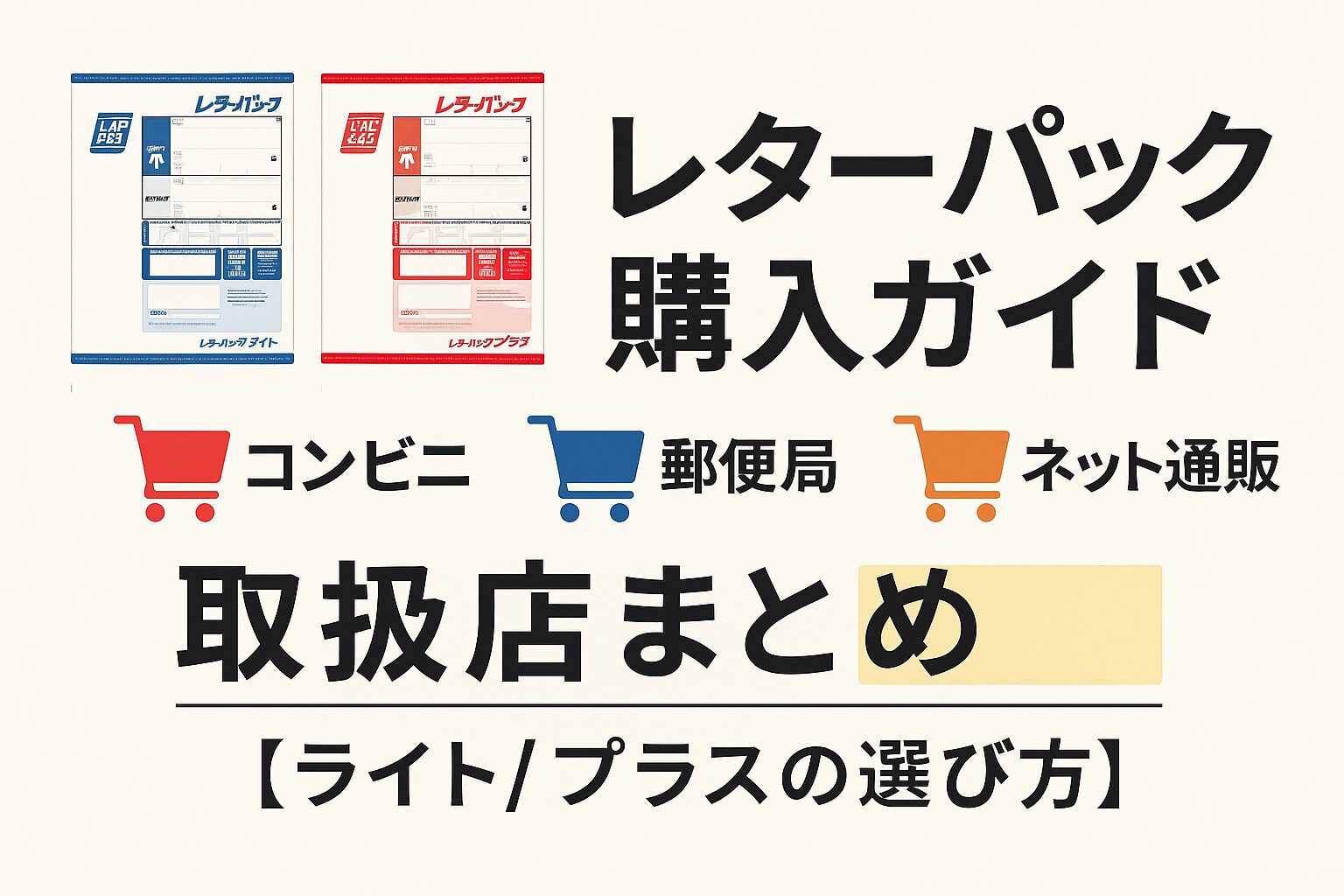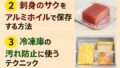荷物や書類を送りたいとき、みなさんはどんな方法を使っていますか?「レターパックってよく聞くけど、実際どこで買えるの?」「ライトとプラスって何が違うの?」と疑問に思ったことがある方も多いのではないでしょうか。
この記事では、レターパックの購入できる場所や、ライトとプラスの違いと選び方をわかりやすく解説!さらに、便利な使い方やビジネスでの応用法まで、今日から使える情報をたっぷりご紹介します。
2025年最新情報をもとに、あなたの発送ライフをもっと快適にするためのガイドとして、ぜひ最後までご覧ください!
\人気商品はコレ!/ 楽天ランキングページはこちら<PR>
\人気アイテムをチェックしよう!/ Amazon売れ筋ランキングはこちら<PR>
コンビニでも買える?レターパックが売っている場所まとめ
郵便局での購入方法と取り扱い時間
レターパックは、日本郵便が提供している全国一律料金の配送サービスです。まず一番確実に手に入る場所は「郵便局」です。郵便局の窓口では、レターパックライト(370円)とレターパックプラス(520円)の両方を購入できます。
営業時間は多くの郵便局で平日9時〜17時ですが、都市部の中央郵便局などでは24時間営業や土日も開いている場所もあります。とくに大きめの「ゆうゆう窓口」がある郵便局なら、平日の夜間や休日でも対応可能です。
また、レターパックは1枚単位からでも買えますし、まとめて10枚、20枚と買うこともできます。封筒タイプになっているので、家にストックしておくといざという時に便利です。
ちなみに、料金は郵便局で購入しても定価のままなので、送料を節約したい場合は後述するネット通販なども比較すると良いでしょう。ただし、信頼性や在庫の確実さで言えば、やはり郵便局が一番です。
コンビニで買えるレターパックの種類
郵便局以外でレターパックが手に入る代表的な場所は「コンビニ」です。特にローソンは、日本郵便と提携しているためレターパックの取り扱いがあります。ライト・プラスのどちらも購入可能な店舗が多いです。
ローソンではレジで「レターパックください」と言えば在庫があればその場で購入できます。レジ後ろに保管されていることが多いので、陳列されていないからといって諦めないでください。
ただし、セブンイレブンやファミリーマートでは基本的にレターパックの販売はしていません(2025年8月現在)。取り扱っているのはあくまで一部のローソンと、それに準ずるコンビニに限られます。
また、コンビニによっては在庫が少ないこともあるので、複数枚欲しい場合は事前に電話で在庫確認をするのが確実です。
大型スーパー・ホームセンターでの取扱状況
意外と知られていませんが、大型スーパーやホームセンターの一部でもレターパックが購入できる店舗があります。たとえば「イオン」や「イトーヨーカドー」、「カインズホーム」などでは、店舗内に郵便窓口(郵便取次コーナー)がある場合があり、そこで購入できます。
これらのコーナーは郵便局が設置しているわけではなく、日本郵便の委託業務をおこなっている店舗で、切手やはがき、レターパックなどを販売しています。
取扱時間は各店舗の営業時間に準じていることが多く、土日や祝日も営業しているのがメリットです。買い物ついでに手に入れられるので、便利な選択肢となります。
ただし、すべてのスーパーで取扱っているわけではないので、こちらも事前に公式サイトや電話で確認すると安心です。
ネット通販での購入は便利?注意点も紹介
レターパックはAmazonや楽天市場、Yahoo!ショッピングなどのネット通販でも購入できます。数枚単位のセット販売が一般的で、自宅にいながら購入できるのが最大のメリットです。
特に10枚、20枚のまとめ買いをしたい場合は、ネット通販の方が在庫も豊富で、郵便局に行く手間も省けます。ただし、販売元によっては送料が上乗せされたり、価格が定価より高いこともあるので注意が必要です。
安全性・信頼性を求めるなら、Amazonの「日本郵便公式ショップ」などの正規取扱店を利用しましょう。
レターパックが買える意外な場所とは?
実はレターパックは一部のキオスクや文房具店、オフィス用品専門店(たとえば東急ハンズやロフトなど)でも取り扱われている場合があります。これらの店舗では企業ユーザー向けに郵便関連商品を扱っているため、レターパックの販売をしていることも。
さらに、オフィスビル内の「ビジネスセンター」や、大学・病院の売店など、日常的に郵送を利用する人が多い施設内では、レターパックの販売が行われているケースもあります。
観光地では、観光案内所やホテルのフロントで取り扱っていることもあるので、旅行中に急に必要になったときでも意外と入手できる場所は多いのです。
レターパックライトとプラスの違いとは?
配達方法の違いをわかりやすく解説
レターパックには「ライト」と「プラス」の2種類がありますが、最も大きな違いは配達方法にあります。
-
レターパックライト:郵便受けに配達されます(不在でもOK)
-
レターパックプラス:対面で手渡し配達、受領印またはサインが必要です
つまり、不在時にも届けてほしい場合は「ライト」、確実に手渡してもらいたいときは「プラス」が向いています。
自宅にいる時間が少ない方や、会社宛てに送りたい場合などはライトが便利です。一方で、オークションの取引や貴重な書類など、「受け取りの証拠」が欲しい場合にはプラスの方が安心です。
さらに、プラスは万が一の時のために記録が残るので、トラブル回避にもつながります。
厚さ制限と重量制限の違い
レターパックライトとプラスでは、封筒のサイズは同じですが「厚さ」と「重さ」に違いがあります。以下の表で整理してみましょう。
| 種類 | 厚さ制限 | 重量制限 | 備考 |
|---|---|---|---|
| レターパックライト | 3cm以内 | 4kgまで | 郵便受けに投函される |
| レターパックプラス | 制限なし(封筒が閉じればOK) | 4kgまで | 手渡し配達、対面受け取り |
ライトは「3cm以内」という制限があるため、たとえば書類や薄手の衣類などには向いていますが、厚みのある物を送るには不向きです。
一方、プラスは厚さに制限がないため、たとえば箱入りの雑貨や小物なども封筒がしっかり閉じられれば送ることができます。重量はどちらも最大4kgまでなので、重いものを送るときには、厚さではなく重さもチェックしましょう。
また、ライトで厚さがオーバーすると返送されるリスクがあるため、心配なときはプラスを選ぶのが無難です。
値段の違いとコスパの良さ
価格面で見ると、レターパックライトは370円、レターパックプラスは520円(いずれも2025年8月現在)となっており、プラスの方が150円高くなっています。
この差額をどう見るかは送る内容によります。たとえば、以下のような場合にはライトで十分です。
-
書類数枚を送るだけ
-
不在でも届けて欲しい
-
コストをなるべく抑えたい
一方で、次のような場合はプラスの方がコスパが良いです。
-
相手に確実に手渡ししたい
-
追跡や受領確認が必要な取引
-
多少厚みのある荷物を送りたい
つまり、どちらがお得かは「何を送るか」「どんな風に届けたいか」によって変わってきます。コスパの面だけを見ても、用途に合った選び方が重要です。
追跡サービスの有無と範囲
レターパックの嬉しいポイントのひとつに「追跡サービス」があります。ライトもプラスも、どちらも追跡番号がついていて、発送後に日本郵便のサイトやスマホアプリで配達状況を確認できます。
追跡できる情報は以下のような流れです:
-
引受(郵便局で受付完了)
-
中継(各地域の配達拠点)
-
配達中(配達員が持ち出し)
-
配達完了(受け取り完了)
ライトの場合は「郵便受けに投函された日時」が表示され、プラスの場合は「誰に手渡されたか」まで確認できます。安心感で言えば、プラスの方が記録も詳細です。
この追跡サービスは無料で利用できるのも大きな魅力で、大事な書類や商品の配送に安心を与えてくれます。
どちらが早く届く?配達スピード比較
ライトとプラスは、基本的にはどちらも「速達扱い」とされており、通常の郵便よりも早く届く傾向にあります。たいていの場合、発送の翌日または翌々日には届くスピード感です。
ただし、実際の配達スピードに若干の違いが出ることもあります。
-
ライト:郵便受けへの配達のため、配達ルートに左右される
-
プラス:対面配達のため、再配達になることもあるが、優先的に扱われることが多い
また、都市部から都市部への発送であれば、どちらもかなり早く届くケースが多いですが、地方や離島などでは、若干の遅延が生じることもあるので注意が必要です。
重要書類や日付に余裕のないものは、なるべく午前中に差し出すようにするとスムーズに届きやすくなります。
目的別!レターパックライトとプラスの選び方
書類や軽量物なら「ライト」が便利な理由
レターパックライトは、特に「薄くて軽いもの」を送る際に非常に便利です。たとえば以下のようなケースです:
-
契約書や請求書、申込書などのビジネス文書
-
履歴書・職務経歴書の郵送
-
薄手の書籍や小冊子
-
USBメモリやSDカードなどの小物類
これらはすべて3cm以内で収まるものであり、重さも4kg以内に収まるため、ライトで送るのがもっともコストパフォーマンスに優れています。
また、ライトはポスト投函で配達完了となるため、受取人が不在でも荷物が届くのが利点です。特に「会社宛て」や「個人宅」で昼間は留守にしている場合に向いています。
郵便受けが小さい場合や、ほかの郵便物と重なって投函されないこともあるため、少し余裕をもってサイズ感を調整すると安全です。
商品発送や大切な荷物には「プラス」が安心
レターパックプラスは、荷物の内容が重要だったり、高い確率で相手に直接届けたいときに最適です。以下のようなケースに特に向いています:
-
フリマアプリ(メルカリ、ラクマなど)の商品の発送
-
サインが必要なビジネス文書や機密書類
-
プレゼントやギフトの郵送
-
貴重な資料・証明書・卒業証明などの発送
-
確実な到着確認を求める場合
最大の安心ポイントは「対面手渡し」であること。受取人が荷物を受け取る際にサインか受領印が必要なため、配達完了が明確に記録に残ります。
また、厚さの制限がなく、封筒が閉じられればOKという柔軟さもあり、プチプチやクッション材を使った梱包が可能。割れ物や壊れやすい商品にも安心して使えます。
ただし、対面配達のため、不在だと再配達になるデメリットも。日中在宅していることが前提になるため、送り先の都合を考えて選ぶことが重要です。
対面受け取りが必要な場合のポイント
対面での受け取りが求められる場面では、レターパックプラス一択と言えるでしょう。特に次のような理由からです。
-
相手に届いた証拠が残る
-
他人に勝手に受け取られるリスクが低い
-
紛失や未着のリスクを軽減できる
-
サインまたは印鑑で受領記録が残る
-
追跡履歴で「配達完了」まで確認できる
このように、レターパックプラスは「配達の安全性・信頼性」を重視する場面に最適。企業間の書類送付や、法律関係の通知文書などにも利用されています。
不在が多い相手には事前に「プラスで送る」と伝えておくとスムーズです。また、再配達はスマホから簡単に依頼できるので、相手が忙しい場合でもある程度安心して使えます。
料金で選ぶ?コスト重視派へのアドバイス
コストを第一に考える方は、やはりレターパックライトを検討するのが良いでしょう。ライトは370円で全国一律の配送料。たとえば、ゆうパックや宅配便を使うより圧倒的に安価です。
それでも以下のようなことを考えるときはプラスの検討価値も出てきます。
-
配送事故やトラブルのリスクが気になる
-
相手が確実に受け取った記録がほしい
-
荷物の中身が高価または重要なもの
この場合、+150円で得られる「対面受け取り」と「記録の明確さ」は、むしろお得とも言えるでしょう。
また、頻繁にレターパックを使う人は10枚単位でまとめ買いすることで在庫を切らさず、郵便局やネットでの購入の手間も減らせます。業務利用なら、年間コストを削減できるメリットも大きいです。
「ゆうパケット」や「クリックポスト」との比較
レターパック以外にも日本郵便には便利な配送サービスがあります。特に「ゆうパケット」や「クリックポスト」は、同じく安価で全国一律料金。以下の表で違いを比較してみましょう。
| サービス名 | 料金 | 厚さ | 配達方法 | 追跡 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| レターパックライト | 370円 | 3cm以内 | 郵便受け | あり | 封筒型・早く届く |
| レターパックプラス | 520円 | 制限なし | 対面手渡し | あり | 重要なもの向け |
| クリックポスト | 185円 | 3cm以内 | 郵便受け | あり | ラベル印刷が必要・安い |
| ゆうパケット | 250円〜 | 1〜3cm | 郵便受け | あり | サイズで料金変動 |
クリックポストやゆうパケットはより安価ですが、事前のオンライン手続きやラベル印刷が必要なため、すぐに使いたい場面では不向きです。
その点、レターパックは「手に入れて書くだけ」ですぐに発送できるシンプルさが最大の強み。急ぎの発送や手間を省きたいときに重宝します。
レターパックの使い方・送り方の基本
書き方のルールと記入時の注意点
レターパックを使う際の基本ルールはとても簡単です。封筒に印刷されている宛名欄に、以下の情報を記入しましょう。
-
差出人の名前・住所・電話番号
-
宛先の名前・住所・電話番号
黒か青のボールペンで書くのが推奨されており、鉛筆や消せるペンは使用NG。書いたあとに消されたり、にじんだりする可能性があるからです。
また、宛先や差出人情報が読みにくいと配達トラブルの原因になるので、なるべく丁寧で大きめの文字で記入しましょう。
英字や外国語の宛先も対応可能ですが、国内宛てであれば必ず日本語で記載を。電話番号も忘れずに書いておくと、不在時の連絡がスムーズになります。
送り状の貼り方とNGな例
レターパックには送り状(伝票)は不要で、封筒に印刷されている宛名欄に直接書き込むだけでOKです。ここが他の配送サービスと違ってとてもシンプルなポイントです。
ただし、注意すべき点がいくつかあります。
-
表面の指定された欄以外には書き込まないこと
宛名は封筒の表面右下に書くエリアがあり、それ以外の場所に記入すると読み取りエラーになる可能性があります。 -
宛先が長すぎる場合は、略さず小さめの字で書く
「〇〇市〇〇区〇〇丁目〇番〇号…」と長くても、きちんと省略せず書くのが基本です。 -
「様」「御中」などの敬称を忘れずに
個人宛には「様」、会社・団体宛には「御中」を必ず書きましょう。
また、封を閉じるときは、しっかりとのり付けやテープ留めをしておくことが大切です。とくに厚みのあるものを入れる場合、自然に開いてしまうことがあるので注意しましょう。
間違って書いた場合は、修正液を使わず、新しいレターパックに書き直すのがルールです。書き損じを防ぐためには、事前に鉛筆で下書きしてからペンで清書するのもおすすめです。
投函できる場所とその方法
レターパックは、郵便局の窓口はもちろん、全国のポストに投函することも可能です。ポストに入れる際のポイントは以下のとおりです。
-
ポストの投入口のサイズを確認(厚さ3cm以内であれば問題なし)
-
夜間や休日でも投函OK
-
ポストに入れた場合、集荷時間によって配達日が変わる
とくにライトはポスト投函向けに作られているので、24時間いつでも手軽に送れるのが魅力です。ただし、プラスは投函も可能ですが、サイズ的にポストに入らないこともあるため、その場合は郵便局の窓口に差し出しましょう。
また、大きめのレターパックを確実に送りたい場合は、ゆうゆう窓口(時間外窓口)を利用するのもおすすめです。
投函後に不安なときは、差し出し証明がもらえる郵便窓口から送ると安心です。証明書をもらえば、差し出した記録が残り、万一のトラブル時に役立ちます。
配達状況の確認方法と追跡サービスの活用
レターパックには追跡番号が付いており、荷物の現在地や配達状況をオンラインで確認することができます。追跡番号は封筒の右上に印字されており、13桁の英数字(例:1234-5678-9012)になっています。
確認方法は以下のとおりです:
-
日本郵便の公式サイトにアクセス(https://trackings.post.japanpost.jp)
-
追跡番号を入力
-
配送状況が一覧表示される
スマホ用のアプリ(日本郵便公式)を使えば、バーコードを読み取るだけで追跡可能なのでとても便利です。
確認できるステータスは:
-
引受(荷物を郵便局が受け取った)
-
中継(途中の拠点に移動中)
-
配達中(配達員が持ち出し中)
-
配達完了(受取人に届けられた)
プラスの場合は、サインした日時まで表示されるため、安心度は高いです。受取人に「もう届いたかな?」と確認する必要がなくなるため、特にビジネスシーンでは信頼につながります。
トラブル時の対応方法や問い合わせ先
万一、荷物が届かない、追跡が止まっているなどのトラブルがあった場合でも、レターパックにはしっかりとしたサポート体制があります。
問い合わせ手順は以下のとおりです:
-
日本郵便の追跡ページで状況を確認
-
解決しない場合は、郵便局の窓口またはお客様サービスセンターへ連絡
-
問い合わせの際には追跡番号を手元に準備
【日本郵便お客様サービス相談センター】
フリーダイヤル:0120-23-28-86
受付時間:平日 8:00〜21:00/土日祝 9:00〜21:00
レターパックには補償が付いていないため、万一の紛失や誤配が起きた場合の返金対応は基本的にはありません。ただし、追跡履歴をもとに調査・対応してくれるため、できるだけ早く問い合わせることが大切です。
封筒の控えや写真を保管しておくと、状況説明がスムーズにできるので、発送前の記録も大事にしておきましょう。
レターパックをもっと便利に使うテクニック
レターパックをストックしておくメリット
レターパックは1枚ずつでも購入できますが、自宅や職場に数枚ストックしておくことで、急ぎの発送にすぐ対応できるという大きなメリットがあります。
例えば以下のようなシーンでストックが役立ちます:
-
締切ギリギリの応募書類の郵送
-
急なビジネス書類の送付依頼
-
フリマアプリの即日発送対応
-
実家や友人への荷物発送
-
大雨や大雪で外出できない日
特にライトとプラスをそれぞれ2~3枚ずつ常備しておくと、送る内容や相手に応じてすぐに使い分けができます。
また、郵便局やコンビニが閉まっている時間帯でも、レターパックさえ手元にあれば記入してポストに投函するだけで完了。時間と手間を大幅に短縮できます。
在庫管理として、購入日を裏面にメモしておくと「いつ買ったか」「使い切っているか」の確認ができて便利です。古くなると汚れたり折れたりしてしまうので、保管は平らな状態で行いましょう。
QRコードやスマホでの追跡確認方法
最近のレターパックには、封筒の右上にQRコードが印刷されていることがあります。このQRコードをスマホで読み取れば、簡単に追跡ページへアクセスできます。
手順はとてもシンプル:
-
スマホのカメラやQRコードリーダーを起動
-
レターパックのQRコードを読み込む
-
自動で追跡ページが開き、配達状況が表示される
この機能は特に外出先や移動中に便利です。パソコンを開かなくても、荷物の状況をすぐにチェックできます。
また、複数の荷物を同時に管理したい場合は、日本郵便の公式アプリ「郵便追跡サービスアプリ」がおすすめ。追跡番号を保存しておけば、配送状況の変化を通知で受け取ることも可能です。
受取人に「今どこにあるか」知らせたい場合は、追跡ページのURLをコピーしてLINEやメールで共有すれば一目瞭然です。
定形外郵便との違いと使い分け
レターパックとよく比較されるサービスに「定形外郵便」があります。どちらを選べば良いか迷う方も多いですが、特徴と違いを理解することで適切に使い分けが可能です。
| 項目 | レターパック | 定形外郵便 |
|---|---|---|
| 配達方法 | 速達扱い・追跡あり | 普通郵便・追跡なし |
| 重さ制限 | 4kgまで | 4kgまで |
| 料金 | 一律370円(ライト)、520円(プラス) | 重量・サイズで変動(120円〜1,040円) |
| 信頼性 | 高(対面可・追跡あり) | 低(ポスト投函のみ) |
定形外郵便は小さな荷物を安く送りたい場合に有効ですが、追跡がないため配送状況がわかりません。また、配達に数日かかることもあり、ビジネスや重要書類の郵送には不向きです。
その点、レターパックは全国一律料金で、追跡ができて速達扱いなので、「ちょっと高いけど安心して送りたい」ときにベストな選択肢です。
法人・ビジネスでの活用事例と応用術
レターパックは個人利用だけでなく、法人やビジネスの現場でも多く利用されています。以下のような使い方が代表的です。
-
契約書、請求書、見積書などの往復送付
-
顧客への資料やDMの発送
-
機密書類や書類原本の送付
-
サンプル品や製品パーツのやり取り
-
社員への在宅勤務用備品の発送
ビジネスでは「スピード」と「確実性」が求められるため、追跡可能で対面受け取りもできるレターパックプラスが好まれる傾向にあります。
また、封筒デザインをカスタマイズして、会社のロゴや住所を印刷することも可能(別途手続き必要)で、ブランドイメージの向上にもつながります。
さらに、毎日大量に発送する企業では、レターパックの使用実績をもとに「取引契約」や「特別取扱契約」を郵便局と結ぶことで、さらなる利便性アップや管理の簡略化も可能です。
まとめ:レターパックの賢い使い方で、発送をもっとスマートに!
レターパックは、使い方次第でとても便利でコスパの良い郵便サービスです。ライトとプラス、それぞれの特徴を正しく理解することで、「ただ送るだけ」から「確実に、安心して、コストを抑えて送る」へと進化します。
どこで買えるかを知っておけば、急な発送依頼にも焦らず対応できます。コンビニ、スーパー、ホームセンター、ネット通販など、意外と身近な場所でも購入できるのは大きな利点です。
また、追跡機能や対面受け取りの有無、厚さや重量制限などを比べて使い分けることで、無駄な出費やトラブルを防ぐことも可能です。とくにビジネス利用や頻繁に発送する人にとっては、ストックやまとめ買いといった活用術も重要なポイント。
「ちょっと送りたい」「でも確実に届けたい」そんな時には、ぜひこの記事を思い出して、最適なレターパックを選んでみてくださいね!